|

*フォトギャラリーのページも是非ご覧下さい*
2016年3月 トレーニングコース(上級)体験談
刺激を受けたAJWCEF上級コース 石橋珠生
 今回、日本とオーストラリアの野生動物保護の現状とその違いや、海外での獣医について知りたいと思い、上級コースに参加させていただきました。AJWCEFの
トレーニで少し知っており、前々から参加してみたいと思っておりました。そして今回チャンス
があり参加できたのはとングコースについては、学校で行われていた水野先生のセミナーても良かったです。コースではコアラ、ポッサムなどの有袋類、ハリモグラなどの単孔類といったオーストラリア特有でまさに「変わっ
た」動物たちやヘビやトリなど普段詳しく見ることのできない動物たちを間近で見て、その治療、リハビリや解剖といった獣医学的な専門的なことも学ぶことが
できました。他に、カヤックでの野生動物観察、コアラ病院や政府保護施設の見学もしました。 今回、日本とオーストラリアの野生動物保護の現状とその違いや、海外での獣医について知りたいと思い、上級コースに参加させていただきました。AJWCEFの
トレーニで少し知っており、前々から参加してみたいと思っておりました。そして今回チャンス
があり参加できたのはとングコースについては、学校で行われていた水野先生のセミナーても良かったです。コースではコアラ、ポッサムなどの有袋類、ハリモグラなどの単孔類といったオーストラリア特有でまさに「変わっ
た」動物たちやヘビやトリなど普段詳しく見ることのできない動物たちを間近で見て、その治療、リハビリや解剖といった獣医学的な専門的なことも学ぶことが
できました。他に、カヤックでの野生動物観察、コアラ病院や政府保護施設の見学もしました。
9日
間で最も印象的であったことは、オーストラリアでは、市民の方々のボランティアや寄付がとても多く、それがなければどの保護施設も成り立たないことです。
そういった市民の方々が多いのは、メディアなどで取り上げられることも多く、動物や自然への関心が高いからだと思いました。また、実習中には政治や社会に
ついても話す機会が多く、関心が高いことを感じました。 私はまだまだ英語、獣医学、野生動物、自然、政治、社会、すべてにおいて勉強不足を痛感しました。これから多くのことを学び、今回の実習を将来活かしていきたいです。また、このような貴重な経験をさせてくださった、AJWCEFの方々、実習先の方々、実習を一緒に受けた方々、この場を借りて感謝申し上げます。
2015年8月 トレーニングコース(初級)体験談 日本獣医生命科学大学 獣医学科 2年 上玉利成美
 私は小さい頃から野生動物が好きで、野生動物の保護に関わる獣医になることに興味を持っていました。この野生動物保護トレーニングコースの存在を知り、今しかできない経験ができると考えて参加しました。 私は小さい頃から野生動物が好きで、野生動物の保護に関わる獣医になることに興味を持っていました。この野生動物保護トレーニングコースの存在を知り、今しかできない経験ができると考えて参加しました。
具体的に15日間の実習では、2グループに分かれてゴールドコーストにあるデイビッド・フレー野生動物公園と、ブリスベンにあるモギル・コアラ病院とで1週
間ずつの実習を行いました。グループのメンバーは北海道や東京などの別々の大学から集まっていて初対面でしたが、皆私と同じような思いで参加していたの
で、すぐに打ち解けて仲良くなりました。実習中の食事は基本的に自炊なので、その日の実習後に皆で食材を買いに行って一緒にご飯を作ったり、次の日に持っ
ていくお弁当のメニューを出し合ったりしました。実習後は疲れていたはずなのに、皆と一緒に生活していると不思議と疲れを感じませんでした。ブリスベンに
あるモギル・コアラ病院の実習では、コアラが入院する部屋の掃除をしてユーカリの葉を入れ替えたり、1頭1頭
に合わせて薬を与えたり、先生の行う治療に立ち会って、治療方法を学んだりしました。大学でもまだ習っていないことを学んだり、立ち会ったことのない手術
を自分の目で見たりしたことはとても印象に残りました。ゴールドコーストにあるデイビッド・フレー野生動物公園では、毎日違う動物の世話をしました。カン
ガルーやコアラだけでなく、ディンゴやカモノハシ、ビルビーなど他では決して触れることのできない動物たちに直接触れて、公園内で働くレンジャーの方達に
直接質問したりできたことは貴重な経験でした。
実習中には他に、寄付金で成り立っているカランビン野生動物病院や、クイーンズランド大学などを訪れ、日本とは違う環境や考え方を知り、日本にいた時とは
違う見方で周りを見ることができるようになった気がします。また、休日に友達とバスやトラムに乗って出かけたり、英語を話したりと、何より現地での生活を
楽しむことが出来ました。2週間本当にありがとうございました。
日本獣医生命科学大学 獣医保健看護学科 及川澄
 私は学校で行う海外実習でAJWCEFの方々にお世話になり、大学で忙しくなる前にもう一度オーストラリアに行きたいと思いで、参加させていただくことにしました。 私は学校で行う海外実習でAJWCEFの方々にお世話になり、大学で忙しくなる前にもう一度オーストラリアに行きたいと思いで、参加させていただくことにしました。
1週目のDavid Fleay Wiledlife Parkでは、日本の動物園とは大きく異なった展示動物の飼育方法やオーストラリア固有の動物について学びました。英語での指示に最初はすごく戸惑いましたが、レンジャーやボランティアの皆さんはとても優しく教えてくれました。
2週目のMogill Koala Hospital では、多くのボランティアさんが野生動物の保護活動に携わっていることを知り、入院しているコアラのお世話をしたりコアラ等の病理解剖の見学をしたりと、日本では決して学べないことをたくさん経験しました。
ま
た、このツアーでは人との出会いもとても素晴らしく、貴重なものでした。同じ参加者でも、他大学であることはもちろん、年齢や現在やっていることなども様
々な人が集まって生活したり、実習場所では年の近いレンジャーやボランティアの方、実習で来ていた他国の学生との交流ができ、世界が広いことを身をもって
感じることができました。
また、自分たちで買い物に出かけて食事をつくったり、バスを使ったりする生活をしたことで、海外での日常生活を少し体験できたことはいい経験でした。
このように、観光や語学留などでオーストラリアに来ていたら絶対経験できなかったことがたくさんあり、今回参加して本当に良かったと思っています。
私が将来野生動物に関わる仕事につくかは分かりませんが、今回で学んだこと感じたことを大切にしてさまざまなことに挑戦していきたいと思いました。
私と2週間共に生活してくれた仲間や実習先でお世話になった方々、そして、この機会を与えてくれたAJWCEFのスタッフの方々に心から感謝しています。ありがとうございました!!!!
学生 Y.T
 今回、AJWCEFさんの2015年度夏季オーストラリア野生動物保護トレーニングコース(初期)に参加させていただきました。 今回、AJWCEFさんの2015年度夏季オーストラリア野生動物保護トレーニングコース(初期)に参加させていただきました。
当
初は互いに初対面の方々ばかりでどうなるだろうと心配ではありましたが、実習や自炊、洗濯など複数人と共同生活をしていくうちに自然と仲良くなることがで
きました。参加している方々も学生から社会人まで幅のある方々が多いため、幅広い交友関係を築くことができることも素敵でした。また、AJWCEFの職員の皆様がとても丁寧で優しい対応をしてくださったことがとても安心できました。実習先の病院や野生動物公園の職員の皆様も、私たちのたどたどしい英語にも丁寧に、また根気強く対応してくださるので実際の英語の勉強にもなりました。
オー
ストラリアでの実習は日本では体験できないものばかりでとても貴重な体験となりました。特にオーストラリア特有の動物種や絶滅の危機に瀕している動物種と
身近に触れ合うことができたことが何より楽しく、また専門知識や技量を学ぶことができたことが自分にとってこれからの糧となったと心から感じています。
日
本とオーストラリアとの野生動物に対する認識や制度の違いを身をもって感じることができたことも大変貴重だと感じました。日本にいるばかりでは他国の制度
やその国の人々の意識を知ることは難しいですが、実際にその仕事についている方々、ボランティアとして参加している方々との交流はとても刺激になり、これ
からの環境保全、野生動物保護について改めて深く考える機会をもらったと思っています。
今
回のスタディーツアーで得た知識や経験を決して無駄にするようなことはせず、深く考え、勉強しながら努力、精進していきたいと思います。トレーニングコー
スに参加させていただくことができ、心から楽しく、本当に良かったと思っています。また機会があれば次回は上級のトレーニングコースに参加できればと考え
ています。
AJWCEF職員の皆様、大変お世話になりました。皆様の今後のご活躍を心から願っています。
帯広畜産大学共同獣医学科 山田 晴日  私
の将来の夢は、獣医師として野生動物に関わることです。今回このトレーニングに参加したのも、自分の夢をより具体化するためでした。実際にオーストラリア
に行って、野生動物保護の現場を見て経験して学んだこの二週間は、今の私そして未来の私にも大きく影響を与えるものになったと思います。 私
の将来の夢は、獣医師として野生動物に関わることです。今回このトレーニングに参加したのも、自分の夢をより具体化するためでした。実際にオーストラリア
に行って、野生動物保護の現場を見て経験して学んだこの二週間は、今の私そして未来の私にも大きく影響を与えるものになったと思います。
オー
ストラリアは野生動物との共存を考えて、様々な取組を行っていました。コアラ病院や野生動物専門の動物病院、野生動物公園、野生動物のリサーチセンターな
どで野生動物を守りながら、日々野生動物とどのように人間が関わっていくべきか検討を続けていました。そのような場所で実際にコアラをはじめとする野生動
物に触れ、世話をして、解剖をすることができたのは、本当に貴重な経験です。日本では見ることもできない絶滅危惧種の世話をしたり、有袋類や単孔類の生態
のレクチャーを受けたり、行動観察で動物の生態や状態を目から学び取ったりと、日本ではまず経験することができないことばかりでした。そして日本では、ま
だまだ野生動物の分野に携わることは難しいけれど、オーストラリアではたくさんの獣医師やボランティアの方々が野生動物保護に携わり、治療や環境保全、社
会教育に取り組んでいたことに驚きました。 また、このコースでは素敵な出会いがたくさんありました。オーストラリアの獣医師さん、レンジャーの方、AJWCEFのスタッフの方、そして何をするにも一緒に頑張った同じ参加者の皆さん、すべての方が私にとってかけがえのない存在となりました。
このトレーニングに参加したことで、夢への大きな第一歩が踏み出せたと思います。オーストラリアの方々が全力で野生動物保護に取り組んでいたように、私も立派な獣医になれるように全力を尽くそうと思います。将来、獣医師として戻ってきます!
2015年3月 トレーニングコース(上級)体験談酪農学園大学 獣医学類 4年 唐澤迪子
 私がこのコースの存在を知ったのは、2年前に大学で行われたAJWCEFの講演会でした。そこで、野生のコアラ専門の国立病院:Moggill Koala Hospitalがあることや、このコースが海外で生活する「トレーニング」も兼ねていることを知りました。さらに、実習先に含まれているCurrumbin Wildlife Sanctuary(CWS)Wildlife
Hospitalは、
パークの運営と寄付金のみで経営している野生動物専門の動物病院です。獣医は野生動物にどのように関わっていけるのか考えていたので、日本には見られない
このような施設がある背景には、人と野生動物とのどのような関係があるのか知りたいと感じていました。また、将来の選択肢として海外はハードルが高いと感
じており、このハードルの高さを少しでも下げたいと考え、参加を決めました。 私がこのコースの存在を知ったのは、2年前に大学で行われたAJWCEFの講演会でした。そこで、野生のコアラ専門の国立病院:Moggill Koala Hospitalがあることや、このコースが海外で生活する「トレーニング」も兼ねていることを知りました。さらに、実習先に含まれているCurrumbin Wildlife Sanctuary(CWS)Wildlife
Hospitalは、
パークの運営と寄付金のみで経営している野生動物専門の動物病院です。獣医は野生動物にどのように関わっていけるのか考えていたので、日本には見られない
このような施設がある背景には、人と野生動物とのどのような関係があるのか知りたいと感じていました。また、将来の選択肢として海外はハードルが高いと感
じており、このハードルの高さを少しでも下げたいと考え、参加を決めました。
CWSの病院では3名の獣医師が勤務しており、実習中も頻繁に野生動物が運ばれていました。特に日本と違うと感じたことは、治療に携わるスタッフが獣医師の2~3倍
ほどもいた事・飼育や事務業務の大部分をボランティアが行っていることでした。動物が重要な観光資源であるがゆえ、国としての動物への関心が高いのだとも
考えられますが、日本よりずっと野生動物が人々に浸透していると感じました。一方、野生動物への餌付けがイベントになっているという面もありました。
オー
ストラリア特有の動物の治療や解剖も多数見ることができ、北半球とは全く違う体の構造は大変興味深いものでした。また、上級コースは獣医師の仕事を間近で
見ることができたので、獣医として野生動物の保護にどうやって関わるか?ということを意識しやすかったです。毎日が驚きに満ち刺激的で、7日間とは思えないほど充実した内容でした。
水野先生
とも様々なお話をしたなかで、『真実は自分で判断しないといけない』『太らされた豚は決して幸せではない』という言葉が印象的でした。日本の・自分の現状
を良しとしてぬくぬくしていては分からないことはたくさんあるのだと思います。国内にいても、アンテナの感度を上げて生活していこうと思います。
最後に、素晴らしい7日間にしてくださった実習先の関係者の皆さま、水野先生・平野さん、実習の仲間達、両親に感謝申し上げます。
2015年3月 トレーニングコース(初級)体験談
上松 伽奈子

初めてAJWCEFのトレーニングコースに参加しました。今の大学から参加したのは私一人でしたし、初めて会う人と海外で2週
間も一緒に過ごすことに最初は不安を感じていました。でも、動物に対する興味と愛情は皆同じでしたし、共同生活なので家事を一緒に行っていくうちに自然
と仲も深まりました。毎晩何を料理するか、明日の自由時間はどこへ遊びに行くか、お弁当は何を作ろうかなど、不安が安心に変わってからは毎日が楽しく、ま
た、スタッフの皆さんや現地の皆さんとは仕事の話だけでなく、仕事後のお出かけやホームパーティーなどにも参加していただいて、和気あいあいと楽しく接し
ていただけて、良い思い出ばかりの2週間になりました。
勉強の方では、動物のバイタルチェックや行動観察、餌の準備から与えるまで、このコースでしかできないたくさんの経験をしました。動物と触れ合いながら、
個々の特徴に気づいたり、生態について学べたり、また、毎日観ているレンジャーさんしか知らない話が聞けたりと得るものがとても多いです。コースに参加し
て様々なことを体験したことで自分が何をしたいのかがはっきりしました。将来の夢について迷っている方は、コースに参加することで何か見えてくると思いま
す。
また、動物を愛でるだけでなく、現在オーストラリアの動物におかれている深刻な問題や生と死の境などを間近で感じることが出来ます。生物界の現状を知る貴
重な体験になるでしょう。ショックを受けることもあると思いますが、動物について学ぶ意欲が強い方は、問題なく超えられると思うので是非、トレーニング
コースに参加して自分の目で確認することをお勧めします。
宮崎大学 農学部 畜産草地科学科 2年
松本昇子
この財団について知ったのは、学生が参加できる野生動物関係の活動を探していた時でした。2週間という短い期間でしたが、学校を、さらには日本を出て違う文化・気候・生態系を感じることができたのは忘れられない大切な思い出です。
オーストラリアでの生活の中で驚いたことの一つに、人がすぐ近くにいても野生動物が逃げないということがあります。いわく、オーストラリアの人々が近くに
動物がいることを気にしないから動物も気にしないのだそうです。こういった習慣や考え方の違いを知ることができました。また、ボランティアの方々や施設ス
タッフの方々と話すことで、自分の国の生物に興味をもつことの重要性を感じました。
ツアーを終えて、野生動物と人間の関係について、各国の文化と野生動物についてもっと学びたいと思いました。座学だけでなく、行動し自分の目で見て回ろうと思います。同じ分野に興味を持つ友人やスタッフの方々との出会いに感謝します。ありがとうございました。
河野実里
 私
は野生動物保護に携える職業に就きたいという目標があり、その道への第一歩として今回のトレーニングコースに参加しました。英語も全く話せず・聞けずの状
態での参加でしたが、一緒に参加して仲良くなった仲間や先生方の助けを借りながら、楽しく充実した実習が送る事が出来ました。 私
は野生動物保護に携える職業に就きたいという目標があり、その道への第一歩として今回のトレーニングコースに参加しました。英語も全く話せず・聞けずの状
態での参加でしたが、一緒に参加して仲良くなった仲間や先生方の助けを借りながら、楽しく充実した実習が送る事が出来ました。
最初の実習場所であるDavid Fleay Wildlife Parkでは、レンジャーさんの作業を手伝いながら、オーストラリア固有の野生動物の生態や飼育方法を学ぶ事が出来ました。レンジャーさんはほんとうにフレンドリーで優しく、疑問に思ったことなどが聞きやすかったです。
次の実習場所であるMogill Koala Hospitalでは、獣医さんの病理解剖を見学したり、野生動物に起きている問題などを教えて頂きました。朝にはボランティアさんと一緒に入院しているコアラのお世話をしました。ボランティアさんからは、ボランティアを始めたきっかけや、コアラに対する思いなどを聞く事が出来ました。
他
にもカヤックで川を下りながら、野生のコアラやコウモリ、ペリカンを見たり、ケアラーさんの家に実際にお邪魔をし、どういったことに気を付けて育てている
か、実際にお世話をする部屋の工夫などを見学しました。また、クイーンズランド大学の見学をし、現地の学生がどういった環境で勉強をしているのかなども実
際に見せて頂きました。
フリーデイの日は、町にでてお買い物したり、海で遊んだりしました。レンジャーさんを呼んで夜はみんなでホームパーティーなどもしました。
この2週間が有意義に過ごせたのも一緒に毎日の実習を乗り越えてきた仲間、私たちにより多くのことを教えてくださった先生方、レンジャーさん、ボランティアさんには心の底から感謝しています。
この経験を活かして、将来の夢へ突き進んでいきたいと思いました。
2014年8月 トレーニングコース(初級)体験談
日本獣医生命科学大学獣医学科 伊藤咲
 今回のトレーニングコースでは、オーストラリアの豊かな自然の中で素敵な仲間とともに学ぶことができ、とても充実した時間を過ごすことができました。行く前には、長いかなと思っていた2週間も終わってみると本当にあっという間でした。 今回のトレーニングコースでは、オーストラリアの豊かな自然の中で素敵な仲間とともに学ぶことができ、とても充実した時間を過ごすことができました。行く前には、長いかなと思っていた2週間も終わってみると本当にあっという間でした。
1週目にお世話になったDavid
Fleay Wildlife Parkでは、オーストラリア固有のさまざまな野生動物の生態や飼育法について学びました。レンジャーさんと一緒にえさをあげたり、飼育施設を掃除したことが1番印象に残っています。
2週
目はモギルコアラ病院にて、獣医さんから解剖学や問題となっている病気など専門的なことを教わったり、ボランティアの方と一緒に入院しているコアラたちの
世話をしました。日本だったら絶対に見ることのできない珍しい動物たちの解剖を見学させていただき、貴重な勉強の機会となりました。
この他にもカヤックに乗って野生のコアラを見たり、ケアラーさんのお宅を訪問させていただいたり、クイーンズランド大学の獣医学部の施設を見学したりなど
さまざまなプログラムがありました。そのどれを通しても感じたことは、野生動物の保護はたくさんの人々の協力のもと成り立っているということです。動物の
ことを第一に考えて、それぞれの人々がそれぞれの立場で動いていました。私もいつか獣医という立場でこの協力の輪に加わりたいと思ったので、これからもっ
と勉強に励んでいきます。
また、お世話になったオーストラリアの人々がとても明るく元気で優しかったおかげで、楽しく学ぶことができ本当に感謝しています。ここでの出会いや経験をこれからも大切にしていきたいと思います。2週間ありがとうございました。
山口京子  英
語もろくに話せず、オーストラリアの動物といってもコアラやカンガルーくらいしか知らなかった私が今回このトレーニングに応募した理由は「楽しそう!おも
しろそう!」という直感のみでした。ですからそんな私にとって、オーストラリアでの生活すべてが新たな発見であり、勉強であり、感動でした。トレーニング
では、実際に現地のレンジャーやボランティアの方々に教わりながら、オーストラリア固有の動物たちを世話したり、またコアラに対してはより具体的にケアを
したり治療している現場を見たり参加させていただいたりしました。コアラのにおいを嗅げただけでも貴重なことなのに…ど
れをとっても人に自慢できる素晴らしい経験ばかりでした!またクイーンズランド大学の先生やコアラ病院のドクターの講義を通して野生動物の生態系について
はもちろん、オーストラリア政府や地域社会が野生動物の保護に対してどんな取り組みをしているのかといったことも学ばせていただきました。 英
語もろくに話せず、オーストラリアの動物といってもコアラやカンガルーくらいしか知らなかった私が今回このトレーニングに応募した理由は「楽しそう!おも
しろそう!」という直感のみでした。ですからそんな私にとって、オーストラリアでの生活すべてが新たな発見であり、勉強であり、感動でした。トレーニング
では、実際に現地のレンジャーやボランティアの方々に教わりながら、オーストラリア固有の動物たちを世話したり、またコアラに対してはより具体的にケアを
したり治療している現場を見たり参加させていただいたりしました。コアラのにおいを嗅げただけでも貴重なことなのに…ど
れをとっても人に自慢できる素晴らしい経験ばかりでした!またクイーンズランド大学の先生やコアラ病院のドクターの講義を通して野生動物の生態系について
はもちろん、オーストラリア政府や地域社会が野生動物の保護に対してどんな取り組みをしているのかといったことも学ばせていただきました。
このような様々なプログラムの中で私の1番の思い出はカヤックで川を下りながら6匹もの野生コアラを見つけたことです!!日本ではペットショップで見るようなきれいな鳥や、見たことのない動物がそこら中にいることを目の当たりにした とき、オーストラリアが野生動物の宝庫だと実感しました。 とき、オーストラリアが野生動物の宝庫だと実感しました。
またこのプログラムが「トレーニング」となっているように、私たちは毎日、近くのスーパーで食材を買って自炊を行ったり、実習先までは自力でバスで行ったりと、オーストラリアでのリアルな生活を経験しました。
このような観光でもなく、短期留学やホームステイでもない、日本ではできない数々の素晴らしい経験は私にとってかけがえのない宝物です!!
岐阜大学 応用生物科学部生産環境科学課程 2年 H.R

私は、中学2年生の時に見たNHKの
ある教育番組をきっかけに多くの動物たちが絶滅していることを知り、その時から将来絶滅危惧種を救うような仕事に携わりたいと思っていました。今回のコー
スに参加したのは、日本と海外で野生動物の保護の制度、現状がどのように違っているのかを体験したいと思ったからです。
このコースに参加して、私は本当に多くのことを学ぶことができました。オーストラリアでも施設によっては全く違った方針が取られているということ、政府が完全に協力的であるとは言えないということ、ボランティアが豊富であるから故に起こる問題等、まだまだ改善す
るべき点は多くありました。また実習中だけでなく、移動中の車内での先生方の体験談や、一緒にトレーニングに参加した仲間との会話、それらの全てから様々
なことを学びました。これらの学び、出会い、経験はすべて私にとってかけがえのない宝物であり、人生に大きく関わるものとなりました。トレーニングコース
を終えて、あの時勇気を出して応募してよかったと心から思います。
日本での野生動物の保護や、生物多様性の保全などの一般に知られている知識は真実とは異なっていることが少なくありません。気になることは自分の足で体験
することが一番だと思います。この経験と参加した人との繋がりを大切にして、これからも夢に向かって頑張りたいと思います。このトレーニングコースで私に
関わってくれた先生方、現地の方々、仲間たちに感謝します。
帯広畜産大学 畜産学部 畜産科学課程 4年 八田朋美
学生最後の夏休みに海外へいこうと思っていた私は、学校でAJWCEFのポスターをみかけました。動物保護を仕事にしたいと思いこの大学に来て、考えが変わり今では全く違った道へ進みつつありますが、私の小さい頃からの憧れそのものだと感じ、すぐに応募しました。
私
が強く感じたことは、オーストラリアの動物保護に対する政府のバックアップが日本よりはるかに優れていること。ボランティア団体、施設の充実にも驚きまし
た。しかし、生態系での保護のため、繁殖機能をもたない動物の安楽死が淡々と行われるなど非常に考えさせられることもありました。
また、自分が21年間生きてきた日本について何も知らないことに気づきました。海外と日本の間に抱える問題、国内の問題。日本の中からでなく、外からの日本を見ていく必要があると思いました。
中でも一番心に残っていることはAJWCEFスタッフのプレゼンテーションのお話でした。自分がやると決めたこと、夢は全力でやろう、踏みとどまらずに行動に移そうと思います。
来年度から私は動物とは離れた仕事につきますが、今回のトレーニングコースで出会った学生、DFWP・MKH、AJWCEFの方々から学んだことを持ち続けて、必ず何らかの方法で動物保護の力になりたいと思います。
このような機会を設けていただいたAJWCEFのみなさん、本当にありがとうございました。
2013年2月 トレーニングコース(初級)体験談
日本獣医生命科学大学 獣医学部
3年 杉浦奈都子  私
は野生動物に関係する職業に就きたいという目標があったことや、前に大学のオーストラリア実習に参加したことで有袋類や単孔類といったオーストラリアの固
有種に興味を持ったため、このコースに参加しました。日本では見ることのできない動物をたくさん見ることができ、また、その動物の世話やどんな問題を抱え
ているのかなど様々なことを肌で感じることができました。オーストラリアでは多くの人がボランティアでコアラ病院の仕事を手伝うなどして野生動物を保護し
ていたり、オーストラリアの固有種のみを飼育し展示する施設があったりと日本より野生動物への関心や教育が高い印象を受けました。しかし、一方で、開発や
自然災害による生息地の減少や分断化、外来種の問題といった日本と同じような課題を抱えている一面もあり、野生動物の保護というものは簡単なものではな
く、多くの人の理解や協力が必要なものだなと実感しました。また、このコースの特徴として、考えや問題の解決法を押し付けるのではなく、現状を教え、どう
すれば野生動物の問題を解決し、人間と共存することができるのかを自分で考えさせてくれます。そのため、トレーニング中にも考える機会が多く、将来自分が
やりたいことを真剣に考えるきっかけにもなりました。このコースで体験したことを活かし、どうすれば野生動物が絶滅することなく人と共 私
は野生動物に関係する職業に就きたいという目標があったことや、前に大学のオーストラリア実習に参加したことで有袋類や単孔類といったオーストラリアの固
有種に興味を持ったため、このコースに参加しました。日本では見ることのできない動物をたくさん見ることができ、また、その動物の世話やどんな問題を抱え
ているのかなど様々なことを肌で感じることができました。オーストラリアでは多くの人がボランティアでコアラ病院の仕事を手伝うなどして野生動物を保護し
ていたり、オーストラリアの固有種のみを飼育し展示する施設があったりと日本より野生動物への関心や教育が高い印象を受けました。しかし、一方で、開発や
自然災害による生息地の減少や分断化、外来種の問題といった日本と同じような課題を抱えている一面もあり、野生動物の保護というものは簡単なものではな
く、多くの人の理解や協力が必要なものだなと実感しました。また、このコースの特徴として、考えや問題の解決法を押し付けるのではなく、現状を教え、どう
すれば野生動物の問題を解決し、人間と共存することができるのかを自分で考えさせてくれます。そのため、トレーニング中にも考える機会が多く、将来自分が
やりたいことを真剣に考えるきっかけにもなりました。このコースで体験したことを活かし、どうすれば野生動物が絶滅することなく人と共 存できるようになる
のかを考え、多くの野生動物を助けていきたいと思います。 存できるようになる
のかを考え、多くの野生動物を助けていきたいと思います。
2012年8月 トレーニングコース(初級)体験談
首都大学東京 都市環境学部 自然文化ツーリズムコース 4年 新井 風音
 参加して本当に良かった。ボランティアや職員の方や研究者や獣医やレンジャーさんやAJWCEF のスタッフの方など、本当にいろいろな人が、それぞれいろいろな葛藤や想いや悩みを抱きながらも、一生懸命、野生動物や自然保護に携わっていることがひしひしと伝わった。そして、そういった生の情報を見た自分も、自分のことや自然保護について深く考えるいい機会となった。また、2週間だけではあるが、海外で初めて会った仲間たちと協力して課題や自炊をして暮らすという「共同生活」もとても役に立った。ルームシェアとなれば、時にはちょっとした対立や嫌なこともあるけれど、それを乗り越えて生活していくことは、社会で働くうえで大切なことだと思う。 参加して本当に良かった。ボランティアや職員の方や研究者や獣医やレンジャーさんやAJWCEF のスタッフの方など、本当にいろいろな人が、それぞれいろいろな葛藤や想いや悩みを抱きながらも、一生懸命、野生動物や自然保護に携わっていることがひしひしと伝わった。そして、そういった生の情報を見た自分も、自分のことや自然保護について深く考えるいい機会となった。また、2週間だけではあるが、海外で初めて会った仲間たちと協力して課題や自炊をして暮らすという「共同生活」もとても役に立った。ルームシェアとなれば、時にはちょっとした対立や嫌なこともあるけれど、それを乗り越えて生活していくことは、社会で働くうえで大切なことだと思う。
最
後に、参加しようか悩んでいるあなたへ。ぜひ思い切って参加してみてください。何でもやってみなければわかりません。私がこんなに参加を進めるのには理由
があります。なぜなら、このコースに参加して「一歩踏み出す勇気」を得た気がするからです。私は観光を学んでいるので、獣医でも生命科学でも農学でもない
私が参加するのは場違いなのではないのかと最初はためらいましたが、自然や動物が好きだったので、学科など気にせずに思い切って参加しましたが、参加して
正解でした。ぜひ自分の五感で感じてみて下さい。何か感じるものや得るものがあると思います。
2012年3月 トレーニングコース(上級)体験談
岡山理科大学 動物学科4年 平井仁智
 私
は、去年の初級コースに続き、今年の春に上級コースに参加しました。今回の上級コースでは、内容が初級よりさらにレベルが高くなり、より充実した実習を行
うことができました。野生動物公園や普段入ることのできない野生動物病院での実習は、とても貴重な経験となりました。実際に野生動物の現状を見て、野生動
物はただ助けるだけではいけないということなど、改めて野生動物を保護する難しさをとても感じました。 私
は、去年の初級コースに続き、今年の春に上級コースに参加しました。今回の上級コースでは、内容が初級よりさらにレベルが高くなり、より充実した実習を行
うことができました。野生動物公園や普段入ることのできない野生動物病院での実習は、とても貴重な経験となりました。実際に野生動物の現状を見て、野生動
物はただ助けるだけではいけないということなど、改めて野生動物を保護する難しさをとても感じました。
このトレーニングコースでは、野生動物の勉強だけではなく、人との関わりもとても大切な1つだと思います。今回、去年の初級コースで出会った人に再び会うことができ、新たな出会いもありました。私と同じように動物について勉強する仲間と2週間供にし、一緒
に買い物に行き、一緒に食事を作ることはとても楽しく、異文化で生活する中でとても励みになりました。今回の上級コースに参加した4人の中で、2人は獣医
学専攻で、私も含め残りの2人は動物科学専攻でした。年齢や学校、専門分野が異なる中で、お互い分からないことはサポートし合い、勉強を深めていくことは
とてもいい刺激になりました。
このトレーニングコースを通して、自分の目で見て経験することでより自分の視野が広がったと思います。私は、初級と上級コース両方に参加することができ、
その両方で得られた知識や経験を今後の勉強に生かしていきたいです。そして、いつかまたオーストラリアに行って野生動物のことを勉強できるよう、日本で勉
強を続けていきたいと思います。
2012年2月 トレーニングコース(初級)体験談
東京農工大学 農学部獣医学科2年 吉本悠人
 今
回のトレーニングコースに参加して、僕はオーストラリアにおける野生動物の基礎的な知識、野生動物が置かれている現状、そしてそれらへの対応を間近で見て
学んできました。オーストラリアでは、野生動物は国の物であり、生態系全体を考えて種を保護するという方針のもとで保護活動が行われており、施設やシステ
ム、保護に携わる人の数などから観ても日本より活動が盛んで、人々の意識が高いように感じられました。しかし、その活動も全てが良いというわけではなく、
非常に考えさせられることも多くありました。 今
回のトレーニングコースに参加して、僕はオーストラリアにおける野生動物の基礎的な知識、野生動物が置かれている現状、そしてそれらへの対応を間近で見て
学んできました。オーストラリアでは、野生動物は国の物であり、生態系全体を考えて種を保護するという方針のもとで保護活動が行われており、施設やシステ
ム、保護に携わる人の数などから観ても日本より活動が盛んで、人々の意識が高いように感じられました。しかし、その活動も全てが良いというわけではなく、
非常に考えさせられることも多くありました。
また、野生動物の勉強だけでなく、人との交流もこのトレーニングコースで得られた大きなものの一つです。一緒にコースに参加した友人たちやAJWCEFの
スタッフの皆さん、各施設の獣医師の先生やレンジャーの方々は皆温かく、楽しい2週間を過ごすことができました。海外での実習ということで、英会話への不
安もありましたが、拙い英語でも何とか意思疎通ができたことがとても嬉しかったです。自信につながるとともに英語力の重要性を認識させられる機会となりま
した。
このトレーニングコースで、野生動物への関心と海外に出ることに対する心持ちの両方に大変良い刺激を受けることができたと思います。機会があれば上級コースにも参加したいと考えています。このような経験が今後コースに参加する人たちにもできたら素晴らしいなと思います。
大学生
日
本では、学校教育やメディアを通して「野生動物はだんだんと減ってきているから、これからは守っていくべきだ」程度の啓発はあっても、やはり、野生動物と
人間との距離自体が、どことなく遠い。私自身、今まで野生動物保護に薄い興味はありつつも、実際に野生動物の置かれている現状について深く知ろうとしたこ
とも、ましては何かをやろうと思ったこともなかった。
こ
の実習では、オーストラリアで実際の野生動物保護の現場を少しでも見ることができ、携わる人々のお話をお聞きできたのが、私にとって1番大きかった。なぜ
野生動物が減るという現象に陥ったのか、これから人間がどうしていかねばならないのか、保護が必要とはいっても、実行にあたって一筋縄でできるものではな
ないこと(国民を支えるための開発と自然温存という、どこの国にもあるジレンマの中で、さらにはそのプロセスで今ある生態系全体のバランスの考慮もしなければならないこと、など)を
知り、そもそも保護とは何なのか何のためなのか、こんなにも深く考えることができたのは初めてだった。私自身がこれから、継続的に、これについて学び、人
と話し、一地球人として自分にできることを行動に移していく必要がある、と考える。このような学びの機会を与えてくれた水野先生をはじめとするAJWCEFのスタッフさん、実習を有意義なものにしてくれたDFWP、モギルのコアラ病院の方々に大いに感謝いたします。
2011年9月 トレーニングコース (初級)体験談
山口大学農学部獣医学科2年 中津由紀子
私
は以前から国際的なものに興味があり、尚且つ野生動物にも興味がありました。そのため、大学在学中に海外で野生動物の実習に参加したいと考えていました。
そんな中、このトレーニングコースの参加者募集のお知らせを見つけました。このコースは、海外で英語を学ぶことと野生動物の実習をすることという、自分の
2つの希望を一度に満たすものであることを確信し、すぐに参加しようと決めました。
オーストラリアでは、とてもたくさんの出会いがありました。とても親切にそして楽しく動物について様々なことを教えてくださったレンジャーさん、オースト
ラリア特有の動物に関してたくさんのおもしろいお話を聞かせてくださった獣医師さん、高い志を持ち野生動物保護活動に励むボランティアの方々、きめ細かい
気配りで私たちのお世話をしてくださったAJWCEFの職員の方々、一緒に自炊から実習まで協力して頑張った他の参加者のみんな。どの出会いも私にとって
とても貴重なものでした。
 このトレーニングコースでは、初めて経験することがたくさんありました。そしていろいろ考えさせられる問題にも何度も直面しました。私たちは、人の手に
よって保護され、野生に戻ることができた動物も見ましたし、一方で安楽死せざるを得ない動物も多々目にしました。そして日本とオーストラリアの野生動物保
護に関する様々な違いや、現地の保護活動における良い面、悪い面の両方を知ることもできました。ここで学んだことは、長い間にわたり考えていくべきもので
あると思っています。
このトレーニングコースでは、初めて経験することがたくさんありました。そしていろいろ考えさせられる問題にも何度も直面しました。私たちは、人の手に
よって保護され、野生に戻ることができた動物も見ましたし、一方で安楽死せざるを得ない動物も多々目にしました。そして日本とオーストラリアの野生動物保
護に関する様々な違いや、現地の保護活動における良い面、悪い面の両方を知ることもできました。ここで学んだことは、長い間にわたり考えていくべきもので
あると思っています。
私はこのトレーニングコースに参加したことで、以前より海外を身近に感じることができるようになりました。将来就きたい仕事の方向性はまだ決めていません
が、今回得たものは自分にとって非常に大きな糧になったことは間違いありません。機会があれば上級コースにも参加したいと考えています。本当にありがとう
ございました。
岐阜大学 応用生物科学部 樽澤優芽子  今
回のトレーニングコースでは、様々な実習の経験を通してオーストラリア固有の野生動物の行動を間近で、肌や五感で感じることができました。それだけではな
く、レクチャーなどで各施設の獣医師の先生やアニマルケアラーの方のお話を直接聞かせて頂くことで、理論や知識が実体験と結びつき、より多くのことを深く
学ぶことが 出来たように感じました。 出来たように感じました。
たとえば、モギルコアラ病院ではコアラの死亡原因に関するお話をお聞きしたり、安楽死に関する資料を頂いたりしました。加えて、実際に交通事故で死亡した
コアラを目の当たりにしたり、安楽死の現場に立ち会ったりすることにより、「頭で覚えた」知識に加え、視覚、嗅覚、聴覚、触覚などを通して「感じた」知識
も得ることができました。
また、野生動物保護のあり方や動物の展示の仕方についても学ぶことが出来ました。今回活動させて頂いたデイビッドフレイワイルドライフパークでの展示は、
以前訪れたオーストラリア国内の他の動物園と比べると、たくさんの相違点が見つかりました。そして、日本での展示方法などとも比較して、動物と人間にとっ
てよりよい展示とはどのようなものなのかを考えるきっかけにもなりました。人間にとっては動物がよく見えれば嬉しいですが、教育上の観点からみると、野生
本来の生き方も見られるのも良いのかな、とも思いました。
在豪日本人の方々や留学生の方とお話させて頂いたこともとても良い経験になりました。いろいろな生き方をされている方々のお話を伺い、大きな刺激を受けました。
2010年9月 トレーニングコース(初級)体験談
麻布大学 獣医学部獣医学科 2年 伊藤ひとみ
最初に見学したカランビン・サンクチュアリ野生動物病院では、人為的なケガではなくオス同士のケンカで傷ついた水トカゲが運ばれてきて診療をしていて驚き
ました。日本における野生動物は、誰のものでもなく放任主義ですが、オーストラリアにおける野生動物は「国の所有物」なので、傷付いた動物がいれば治療す
るのかな、と思いました。オーストラリアと日本との野生動物に対する扱いが異なっていることに興味を持ちました。
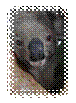  そ
れからブリスベンへ移動し、モギルコアラ病院に3日間実習させてもらいました。安楽死させるコアラが多くとてもショックを受けました。安楽死させた個体
は、私たちの勉強のために解剖させてもらいました。オーストラリアの獣医学生でもなかなかできない貴重な体験をすることができました。ちゃんと1頭1頭解
剖するにあたって政府から許可を得るそうですが、安楽死させた個体で勉強させてもらう、このような献体制度が日本でもあれば良いな、と思いました。 そ
れからブリスベンへ移動し、モギルコアラ病院に3日間実習させてもらいました。安楽死させるコアラが多くとてもショックを受けました。安楽死させた個体
は、私たちの勉強のために解剖させてもらいました。オーストラリアの獣医学生でもなかなかできない貴重な体験をすることができました。ちゃんと1頭1頭解
剖するにあたって政府から許可を得るそうですが、安楽死させた個体で勉強させてもらう、このような献体制度が日本でもあれば良いな、と思いました。
植林もやらせてもらいました。近年、土地開発が進み、ユーカリが伐採されて減少し続けており、病院の近くにプランテーションを作っているそうです。
次に見学したイプスイッチコアラ保護協会で活動をするボランティアの方から、「コアラの保護で一番重要なのは、子どもをちゃんと野生復帰させることです。
1頭1頭助けるのは大事なことだけれど、最近では生息地をいかに残すか、ということに主旨が移ってきています。」という話を聞き、モギルコアラ病院で体験
した植林の重要さに改めて気付かされました。
その後、ゴールドコーストにあるデービッドフレイ野生動物公園で3日間実習を行いました。ワニ、鳥類、木登りカンガルー、ワラビー、絶滅危惧種の鳥などの
餌やりをしました。エサのやり方には、それぞれ工夫があり、日本の動物園よりもエンリッチメントが意識されている印象を受けました。また、展示されている
動物たちがオーストラリア固有種だからこそなのだと思いますが、動物園の設計がとても開放的で驚きました。
最後に見学したデイジーヒル・コアラセンターでは、午前中に車で移動しカラーを付けたコアラをトラッキングしました。最初はラジオを頼りに移動しますが、
コアラがいる近辺に到達すると、木にコアラが登った跡が残っていないか、辺りにフンが落ちていないかなどをチェックしながら探します。なかなか見つからな
いものかと思っていましたが、車を降りてから15分くらいで見つけることができました。トラッキングは何もかもが初めての体験だったのでとても面白かった
です。
トレーニングコースの2週間は、日本では経験できない、すばらしい体験ばかりでした。また、お世話になったAJWCEFの方々をはじめ、現地のレンジャー、獣医師の先生方から聞いた様々なお話はとても印象に残っています。オーストラリアでの全ての出会いに本当に感謝しています。トレーニングコースに参加できて良かったです。
日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 2年 森 春子
いろいろな人と出会えたこと、そしてたくさんの事を学び、体験することができて、とても充実した15日間でした。オーストラリアと日本は同じ島国であるため、特殊な動植物がいるのは同じであるということは知っていたものの、実際にオーストラリア固有の動植物を間近に見、触ったのは初めてで、毎日発見することが多々ありました。
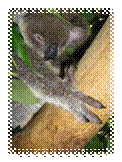 特
に驚いたのはコアラの手の形です。当然のように人間と近い形をしていると思い込んでいたので衝撃を受けました。またコアラはオーストラリアではたくさんい
るのだろうとも思っていたのですが、実際は減少傾向にあって、市民が率先して保護活動を早めに始めているということを知って驚きとともに、市民の行動力に
とても感心しました。その他にもたくさんの動物の世話を体験したり、動物自体のことを学んだりして動物の知識が増えた喜びや、動物の尊さを改めて感じまし
た。可愛くて不思議で興味の底が尽きそうにない動物たちを守っていくためにこれからも活動に参加していきたいと思います。 特
に驚いたのはコアラの手の形です。当然のように人間と近い形をしていると思い込んでいたので衝撃を受けました。またコアラはオーストラリアではたくさんい
るのだろうとも思っていたのですが、実際は減少傾向にあって、市民が率先して保護活動を早めに始めているということを知って驚きとともに、市民の行動力に
とても感心しました。その他にもたくさんの動物の世話を体験したり、動物自体のことを学んだりして動物の知識が増えた喜びや、動物の尊さを改めて感じまし
た。可愛くて不思議で興味の底が尽きそうにない動物たちを守っていくためにこれからも活動に参加していきたいと思います。
日本獣医生命科学大学3年 菅原 愛
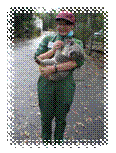 オーストラリアでしかできない非常に貴重な経験をたくさんする事が出来ました。AJWCEFスタッフ、現地のレンジャー、獣医師、このコースで共に学んだ友人たちとの出会いはとても刺激になり影響を受けました。 オーストラリアでしかできない非常に貴重な経験をたくさんする事が出来ました。AJWCEFスタッフ、現地のレンジャー、獣医師、このコースで共に学んだ友人たちとの出会いはとても刺激になり影響を受けました。
オーストラリアにしか居ない個性豊かな面白い動物たちがたくさん居ました。デービットフレイ野生動物公園では飼育作業をお手伝いさせて頂くことで、その
生態や動物公園で行われている保護繁殖、教育普及への取り組みについて学ぶことができました。レクチャーと実習が並行してあるので、レクチャー内容を、実
習で確かめることができ、知れば知るほど動物たちの魅力にどんどんとはまっていきま
した。動物たちが、自然に近い状態で飼育され、生き生きとしていることが印象的でした。
街中にも動物がたくさん居ました。夜、宿泊場所で寝る前、何かの鳴き声がうるさいと思って皆で外に出てみたら、子連れのポッサムが木の上でコウモリを威嚇していました。そのような野生の動物たちとの出会いも、とても面白かったです。
モギルコアラ病院では、毎日コアラが保護されていました。傷ついたコアラたちの運ばれてくる原因に少なからず人間が関わっていることを知り、
実際にそのようなコアラを見たことで、コアラたちを守るために何とかしなければならないという危機感を感じました。亡くなったコアラの解剖をさせて頂いた
ことで、体の特徴を細かくみることができ、有袋類特有の繁殖に関わる生殖器をみられたことは、日本では絶対にできない貴重な経験であり、とても勉強になり
ました。
オーストラリアでは、国民の野生動物に対する意識が日本に比べてとても高いと感じました。それにも関わらず、希少な動物たちはどんどん数を減らしていま
す。オーストラリアで学んだたくさんのことを活かして、これから私は人と動物の共生できる道を探していきたいと思いました。
TOPへ戻る←
|